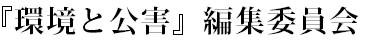第54巻第1号 2024年7月
| タイトル | 執筆者 | 頁 | |
|---|---|---|---|
| リレー・エッセイ | オッペンハイマーと「ノーモア原発公害!」 | 寺西俊一 | 1 |
| 特集1 | 有機フッ素化合物(PFAS)の環境中への広がりと対応 | 2 | |
| 特集1 | 国内外のPFAS への取り組みと国際的な化学物質管理の動向 | 中地重晴 | 2 |
| 特集1 | 国内の汚染の状況:問題発覚初期の調査と近年の動向 | 原田浩二・藤井由希子 | 8 |
| 特集1 | ペル及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)に対する国内外の政策動向 | 井上知也・後藤嘉孝・大野浩一 | 14 |
| 特集1 | PFAS 問題に関する国内の社会的反応:個別事例の経緯に着目して | 村山武彦 | 20 |
| 特集1 | PFAS 汚染は「いのちと人権の問題」:民医連事業所としての使命,SDH, HPH の視点で地域住民の健康不安をサポート | 蓮池安彦 | 26 |
| 特集1 | 沖縄のPFAS 汚染問題:最大の障害は日米地位協定 | 桜井国俊 | 33 |
| 特集2 | 能登半島震災が浮き彫りにする政策課題 | 39 | |
| 特集2 | 「災間」としての能登半島地震の課題:縮小社会における大災害の幕開け | 石原凌河 | 39 |
| 特集2 | 能登半島地震から考える過疎農村地域の維持可能性 | 佐無田光 | 45 |
| 特集2 | 能登半島地震で露呈した原子力防災の破綻 | 上岡直見 | 51 |
| 特集2 | 能登半島地震と水道事業:復旧と持続可能な水道事業への課題 | 武田公子 | 57 |
| 特集2 | 《座談会》能登半島震災は何を問うているか:現地視察を踏まえて | 石原凌河・和田一哉・石倉研・大島堅一・佐無田光・茅野恒秀・山下英俊 | 63 |
| 書評 | 高木竜輔・佐藤彰彦・金井利之編著『原発事故被災自治体の再生と苦悩:富岡町10 年の記録』 | 藤川賢 | 71 |
第54巻第2号 2024年10月
| タイトル | 執筆者 | 頁 | |
|---|---|---|---|
| リレー・エッセイ | いまこそ常設の防災復興庁を | 長谷川公一 | 1 |
| 特集1 | 水俣病をめぐる裁判の動向――ノーモア・ミナマタ第2次訴訟を中心に | 2 | |
| 特集1 | 近畿・熊本・新潟判決の比較検討 | 吉村良一 | 2 |
| 特集1 | 疫学研究の位置づけについて | 渡邉知行 | 10 |
| 特集1 | ノーモア・ミナマタ第2次訴訟の各地裁判決の意義と問題点――医学的観点から―― | 高岡滋 | 16 |
| 特集1 | ノーモア・ミナマタ第二次訴訟における国賠責任否定論の行方 | 清水晶紀 | 22 |
| 特集1 | 水俣病被害者互助会義務付け訴訟の現状と課題 | 番園寛也 | 28 |
| 特集1 | 新潟水俣病第二次棄却処分取消し・行政認定義務付け訴訟――認定基準の見直しこそ,水俣病全面解決のカギ―― | 萩野直路 | 32 |
| 特集1 | 被害救済のあり方――熊本・水俣を中心に―― | 尾崎寛直 | 36 |
| 特集1 | 被害救済のあり方――新潟を中心に | 関礼子 | 40 |
| 特集2 | 沖縄の自然・文化と基地 | 44 | |
| 特集2 | 特集にあたって | 大久保規子 | 44 |
| 特集2 | 辺野古新基地建設を巡る訴訟の現状――住民の抗告訴訟―― | 赤嶺朝子 | 45 |
| 特集2 | 海に地主はいない――浦添西海岸の今と未来―― | 鹿谷麻夕 | 51 |
| 特集2 | 自衛隊訓練場計画を断念に追い込んだ闘い――沖縄うるま市からの報告―― | 伊波洋正 | 55 |
| 特集2 | 沖縄ジュゴンの誕生――民俗学のパースペクティブ―― | 藤井紘司 | 59 |
| 現地報告 | 自然と暮らしを破壊する物流・データセンター開発と住民運動――東京・昭島「昭和の森」から―― | 浅田健志・河野環樹・二ノ宮リム さち | 63 |
| 投稿論文 | 小型風力発電の導入によって残された地域課題――北海道内4自治体へのヒアリング調査をもとに―― | 寺林暁良・藤井康平 | 65 |
第54巻第3号 2025年1月
| タイトル | 執筆者 | 頁 | |
|---|---|---|---|
| リレー・エッセイ | 環境権の法制化に向けて――報告要旨 | 淡路剛久 | 1 |
| 特集1 | 阪神大震災30周年アスベスト被害の再検証 | 2 | |
| 特集1 | 阪神・淡路大震災時のアスベスト飛散状況の再検証 | 中地重晴 | 2 |
| 特集1 | 阪神大震災のアスベスト被害に関するアンケート調査から見えてくるもの | 南慎二郎 | 8 |
| 特集1 | 震災アスベスト被害の経験を語り継ぐ――「時間の壁」を乗り越えるために | 原口剛 | 14 |
| 特集1 | 阪神・淡路大震災後の解体作業に関するアスベスト被害とこれからの可能性 | 伊藤明子 | 20 |
| 特集1 | 災害時の石綿対策と法規制――阪神淡路大震災から能登半島地震まで | 外山尚紀 | 26 |
| 特集1 | 《座談会》災害とアスベスト・阪神淡路30年プロジェクトの取り組みについて | 飯田勝泰・伊藤明子・上田進久・永倉冬史・西山和宏・中地重晴(司会) | 32 |
| 特集2 | 日本環境会議東京大会 | 40 | |
| 特集2 | 環境から軍事を問う | 桜井国俊 | 40 |
| 特集2 | 南西諸島の軍事要塞化に係る環境アセスメントの課題――求められる自治体条例の改正と国際人権法を通じた取り組み | 砂川かおり | 46 |
| 特集2 | 平和自治権と生命・環境の維持 | 白藤博行 | 52 |
| 特集2 | 地域社会・地方財政から南西シフトと軍事要塞化を問う――伊江島と与那国島を中心に | 関耕平 | 58 |
| 特集2 | もし能登半島地震時に原発が稼働していたら――志賀・珠洲原発からの放射性物質拡散シミュレーション | 上岡直見 | 64 |
| 特集2 | 第39回日本環境会議東京大会――開催記録 | 山下英俊 | 68 |
| 書評 | レベッカ・エリス著,大森正之訳『ミツバチたちの危機を超えて――ポスト資本主義の農業へ』 | 太田和彦 | 71 |
第54巻第4号 2025年4月
| タイトル | 執筆者 | 頁 | |
|---|---|---|---|
| リレー・エッセイ | トランプ政権は、パリ協定離脱を撤回すべきだ | 永井進 | 1 |
| 特集1 | 気候訴訟の最新動向 | 2 | |
| 特集1 | 特集にあたって | 島村健 | 2 |
| 特集1 | 神鋼石炭火力発電に対する市民の運動 | 廣岡豊 | 3 |
| 特集1 | 神戸石炭火力訴訟 | 杉田峻介 | 11 |
| 特集1 | 世界の気候訴訟の動向 | 一原雅子 | 18 |
| 特集1 | 若者気候訴訟のめざすもの――温暖化を止め、明日を生きるための挑戦 | 浅岡美恵 | 25 |
| 特集2 | 大気汚染地域の再生と福祉・環境のまちづくり:水島から | 29 | |
| 特集2 | 「環境再生のまちづくり」の今日的展開と協働の深化――特集にあたって | 除本理史 | 29 |
| 特集2 | 水島における公害問題と医療生協――倉敷医療生協の医療社会活動からの照射 | 尾崎寛直 | 31 |
| 特集2 | 公害の学びが協働を豊かにする――倉敷市水島での取り組み | 林美帆・除本理史 | 38 |
| 特集2 | 《事例報告》NPO法人かけはしと介護・福祉事業の地域連携 | 田邊昭夫・猶原眞弓・山本幸子 | 44 |
| 座談会 | 《座談会》水島のまちづくりとJEC大会への期待 | 林美帆・福田憲一・古川明・三村聡・三宅康裕・除本理史 | 46 |
| 小特集 | 北海道の自然公園破壊 | 54 | |
| 小特集 | 北海道の自然公園がいま直面すること | 在田一則 | 54 |
| 小特集 | 知床岬の携帯電話基地局整備の問題と対応――失いかけた世界自然遺産の核心部の価値 | 大野正人 | 59 |
| 投稿論文 | 日本の気候変動訴訟における司法アクセスに対する当事者の認識 | 一原雅子 | 62 |
| 書評 | 梶原健嗣『都市化と水害の戦後史』 | 礒野弥生 | 69 |
| 書評 | 清水晶紀『環境リスクと行政の不作為』 | 下山憲治 | 70 |
| 書評 | 除本理史・河北新報社編『福島「オルタナ伝承館」ガイド』 | 池田千恵子 | 71 |