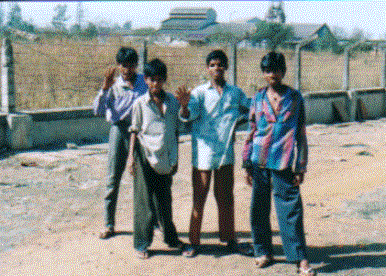アジア太平洋
インターネット環境情報ガイド
2000年版
アジア太平洋環境情報ネットワーク
Environmental Information Network for Asia and Pacific (EINAP)
E-mail: webmaster@einap.org
1.これまでの経緯
来たるべき21世紀に向けて、いわゆる地球環境保全がますます重要な課題となっているが、この地球環境保全への道は、とりわけアジアの各国・各地域での具体的な環境保全の取り組みの前進とそれにもとづくアジアにおける新たな環境協力の多様な展開なくしては切り開かれていかない。また、このような課題を担っていくためには、アジアにおける環境NGOの相互協力と連帯のためのネットワークの発展が不可欠である。
近年急速に世界的に普及したインターネットを効果的に活用することによって、こうした地理的に分散した主体同士が極めて迅速かつ安価に情報交換することが可能となる。しかし、現状ではアジア地域のNGOレベルでのインターネットの利用は未発達の段階にある。したがって、NGOレベルでのインターネットを利用した情報の共有化を推進することが、21世紀の地球環境保全のためには急務であるといえよう。
以上のような認識のもと、われわれは1998年度、独自のネットワーク・サーバーを構築し、当研究会のホームページやメーリング・リストを立ち上げ、それを用いてアジア地域の環境情報の収集、公開、共有の推進を図った。並行して、1998年秋にシンガポールで行われた「第4回アジア太平洋NGO環境会議」に参加し、アジアにおけるインターネットを利用した環境情報の共有化について各国の関係者とともに検討を行い、協力者を募った。
1999年度は、日本からアジアへの情報発信(すなわち、日本の公害とその克服の経験のアジアへの紹介)と、アジアから日本への情報発信(すなわち、インターネットを通じてみるアジア各国の環境情報の紹介)との2面から、インターネットを用いた環境情報の収集と発信を進めてきた。
2.本年度の活動の概要
本年度は、昨年度整備したネットワーク基盤を用い、インターネットを用いたアジア地域の環境情報の収集と発信の作業を本格的に開始した。本年度の活動には、大きく二つの柱がある。一方は、日本からアジアへの情報発信であり、具体的には、足尾や水俣など、日本の公害とその克服の経験を英文で図表を交え、わかりやすくアジア地域に発信する作業である。個別事例の紹介に限らず、『環境と公害』(旧称『公害研究』)の過去30年間にわたる公害に対する取り組みの成果を英文総目次として紹介するといった、学術的価値のある情報の発信も進めた。
もう一方の柱は、アジアから日本への情報発信であり、具体的には、インターネットを通じてアジア地域の最新の環境情報を収集し、地域別、話題別などに整理してホームページ上で発信する作業である。情報の収集に際しては、各国のインターネット事情の共通性と差異が明らかとなった。また、収集した情報の整理、発信の方法についても、先行事例を参考にしつつ、独自の方針を模索する必要があった。
以下の3章、4章では、本年度の研究会活動の2つの柱のうち、重点的に調査を進めたアジアから日本への発信、すなわちアジア太平洋地域の環境関連情報の現状とその公開方法について焦点を当て、その研究成果の一端を紹介したい。なお、同様の内容をEINAPホームページ(http://www.einap.org/)でも公開している。
3.環境情報ガイドのあり方
環境情報の共有は、永続可能な開発へ向けて必要不可欠なものである。環境が破壊されているという情報が広く市民に伝えられなければ、市民の環境保全への努力は、不充分なものとなってしまう。このような認識は、地球サミットなどの国際会議でもうちだされている。
例えば、『環境と開発に関するリオ宣言』では、以下のように、環境情報の重要性を指摘している。
「原則10 環境問題は、それぞれのレベルで、関心のあるすべての市民が参加することにより最も適切に扱われる。国内レベルでは、各個人が有害物質や地域社会における活動の情報を含め、公共機関が有している環境関連情報を適切に入手し、そして、意志決定過程に参加する機会を有しなくてはならない。各国は、情報を広く行き渡らせることにより、国民の啓発と参加を促進し、かつ奨励しなくてはならない。(後略)」 (『環境と開発に関するリオ宣言』)
また、アジェンダ21でも、第40章「意志決定のための情報」で、環境情報の重要性が指摘されている。
「持続可能な開発においては、誰もが広い意味での情報の受け手であり、送り手である。この広い意味での情報の中には、データ、情報、まとまった経験と知識が含まれる。情報に対するニーズは、国家あるいは国際レベルにおける高位の意志決定者から草の根の個人レベルまで、あらゆるレベルで発生する決定がより一層信頼できる情報に基づいて下されるようにするために、以下に示す2つの分野におけるプログラムを実施する必要がある。
(a)データ格差の解消
(b)情報の利用性の向上
(『アジェンダ21』)
国際的に環境情報の共有の重要性が認知される以前から、各国政府は、市民や研究者からの要求などを受けて、環境白書や環境統計の発行や環境指標の公開などを行ってきた。
これら伝統的な出版物による情報公開に加え、1990年代半ばから、インターネット上での情報公開がなされるようになってきた。環境省などの政府機関では、環境法や環境白書の内容の紹介から、毎日の大気汚染指標の公開といったさまざまな情報をインターネット上で公表している。また、公害反対運動、自然保護運動などを展開しているさまざまなNGOもホームページを開設し、それぞれの活動内容など、さまざまな環境情報を掲載するようになってきている。
これらのインターネット上の情報源は、アジアの環境問題研究にとってかかせないものとなってきている。また、環境教育の観点からもこれらの情報源が利用され、アジアの環境問題について理解を深めることが求められているといえよう。
インターネット上のサイトは、日々増加しており、膨大な量となってきている。あまりに膨大な量となっているため、さまざまな検索サイトを利用しても、自分の欲している情報にはなかなかたどりつけない。このような時に役立つのが、インターネットのサイトを紹介している出版物である。しかし、既存のインターネットのサイトを紹介している日本の出版物は、日本語のホームページを中心としており、アジア諸国の情報源については十分に伝えていない。英語では、環境関連のホームページを紹介している出版物が次々に出版されているが、欧米のホームページが中心で、アジア地域の情報源については、十分に扱われているとはいえない。インターネット上の環境情報を中心とした「アジア環境情報ガイド」が求められているのである。
「アジア環境情報ガイド」は、アジアの環境問題を研究する者にとって、貴重な情報源となるのみならず、ひろく利用されるものとなると考えられる。NGOなどが活動を行う際にも、アジア各国の情報は、アジア各国が共通に抱えている問題をみつけ、経験を共有する一助となる。アジアの環境問題を学ぼうとする大学院生、大学生には問題を発見し、基本的な情報を得る第1歩となるだろう。また、高校での英語教育や社会科教育でも、英語で発表されているアジアの環境問題についての情報は、生徒の興味関心をひくことが予想される。
「アジア環境情報ガイド」の内容については、詳しくは、これからの連載で見ていただくことになるが、下記の4つに整理するとわかりやすい。
1)一般的な情報源
各国の英字紙、政府機関リンクサイト、サーチエンジンなど。
2)テーマ別環境情報源
英語を中心としたそれぞれのテーマについての情報源。
3)各国・地域別環境情報源
現地語を含む各国・地域の環境情報源。
4)個別の事件・問題の情報源
水俣、ボパールなど象徴的な問題についての情報源。
将来的には、2)のテーマ別の環境情報源を、環境媒体別など、より体系的に分類することも考えられる。
さまざまな情報源を、その内容を評価しながら紹介することは、ホームページの作成者にも良い刺激を与えると考えられる。「環境情報ガイド」は、より詳しい、よりわかりやすい環境情報の提供をうながす効果を期待できるのである。
特に、これまでのところ日本からの英語での環境情報の発信はあまり多くない。日本の1950-70年代にかけての公害経験や、現在も抱えているさまざまな環境問題に関して情報を発信していくことは、日本以外のアジア諸国にとって、その発展の方向性や対策の取り方を考えていく際の参考となるはずである。環境庁のホームページでは、法律など政府の資料や施策などについては情報が得られる。しかし、より具体的に、どのような環境問題がクローズアップされているのか、紛争が起こっているか、政府の施策に対する批判などの多角的な情報が日本から発信されてしかるべきである。また、政府の情報発信に比べるとNGOの情報発信は、まだまだ少ないと言わざるを得ない。「アジア環境情報ガイド」が、日本からの情報発信も促し、質を向上させていくきっかけとの一つとなることを願っている。
先に述べたように、1992年の地球サミットで採択されたアジェンダ21などでも、環境情報の共有は、多くの人々が環境問題に取り組んでいくための方策のひとつとして重視されている。本連載は、アジアの環境問題について研究をしてきた研究者が、それぞれが蓄積してきた情報源を詳しく紹介するものである。この「アジア環境情報ガイド」の連載を、環境情報の発信と共有を促し、環境教育を促進、環境問題研究を深化させる一助としたいと考えている。
4.アジアにおける環境情報の現状
4.1 一般的な情報源
1)新聞情報
筆者の一人である宮本は、当時の状況を振り返りつぎのように述べている。
当時、私は公害を一般市民はもとより、研究者にも日常的に発生する深刻な社会問題としてどのように認識させるかで悩み、四大全国紙を調べたが外国の例の紹介ぐらいで不十分であった。そこで一県一紙の四六の地方紙を学生諸君の援助を得て全て調べて公害年表をつくり、それを日本の公害地図として『恐るべき公害』の冒頭に発表した。この公害地図を見ると、1960年代初頭に大都市圏のみならず、全国で深刻な公害事件が起こり、自然環境の破壊が進んでいることが明らかとなり、公害への関心は急速に広がった。」(宮本(2000))
宮本が述べているように、地方紙を利用した背景には、全国紙が公害問題の重要性を十分に認識していなかったことがある。水俣病についての朝日新聞の報道をとってみても、公害問題が広く社会問題として認識される前には、全国版に記事が掲載されることは少なかったという(朝日新聞1995年5月27日)。全国の読者が関心を持つような事件ではないと判断されたのであろう。
アジアなどの諸外国の環境問題についても、日本の企業やODAが直接関与していなければ、日本の新聞の国際欄などで扱われることは少ない。たとえば、1999年12月から2000年の1月にかけて、日本からのフィリピンに不正に輸出された医療廃棄物について新聞やテレビで盛んに伝えられたが、1990年代半ばには、アジア各国で、廃棄物の不正輸入がしばしば問題となっていた。1993年には、インドネシアの港で、オランダなどからの廃棄物入りのコンテナが68個置き去りにされていることが明らかになり、また、1995年前後にはアメリカなどから廃棄物が中国に輸出され「洋ゴミ」問題として、おおき問題となった。1998年末には、台湾から水銀入りの産業廃棄物がカンボジアへ輸出され、産業廃棄物を放置された村の住民が暴動を起こしている。これらの事件については、日本の新聞では、単発的に取り上げられることはあっても、経過を継続的に詳しくとりあげられることはほとんどない。アジアの環境問題を知るためには、現地で発行されている英字紙や現地語紙に目を通す必要がある。なお、日本の新聞によるアジアの環境問題に関する報道について、アジア各国での報道されている内容と比較したものに、小島(1996)がある。
新聞などのマスメディアの情報は、二次情報ではあるものの、各地の問題を概観する上では、欠かすことのできない情報源といえる。各国の新聞が解説しているホームページでは、過去の記事の検索も容易にできるようになっており、どのような環境問題が発生しているかについて、政策がとられているかなどについて、貴重な情報を提供している。
【世界各国の新聞へのリンク】
国ごとに、アクセス可能な新聞が網羅されている。
Yahoo! の英語版、www.yahoo.comのカテゴリーから、たどるのもよい。
【アジア諸国の英字新聞】
|
|
新聞名
|
アドレス
|
過去の記事の検索
|
登録/有料/無料
|
|
韓国
|
The
Korea Herald
|
可
|
無料
|
|
|
中国
|
人民日報
|
可
|
無料
|
|
|
China
Daily
|
可
|
無料
|
||
|
香港
|
South
China Morning Post
|
可
|
検索無料
記事は有料 |
|
|
Hong
Kong Standard
|
可
|
有料
|
||
|
フィリピン
|
Philippine
Daily Inquirer
|
可
210日間 |
無料
|
|
|
タイ
|
Bangkok
Post
|
可
|
無料
|
|
|
The
Nation
|
可
|
無料
|
||
|
マレーシア
|
New
Straits Times
|
可
|
7日間無料その他有料
|
|
|
シンガポール
|
The
Straits Times
|
可
|
無料
|
|
|
インドネシア
|
Jakarta
Post
|
可
1994.6− |
登録必要
|
|
|
インド
|
The
Times of India
|
可
|
無料
|
参考文献
庄司光・宮本憲一『恐るべき公害』岩波書店 第1章
小島道一「新聞で見るアジアの環境問題」(『アジ研ワールド・トレンド』(特集−アジアの環境問題を考える−)1996年6月号)、アジア経済研究所、pp.10-13。
宮本憲一「「環境の世紀」を求めて:20世紀を振り返る」『世界』2000年2月号、岩波書店。
4.2 テーマ別環境情報源
1)インターネットを使ってエネルギー・環境問題を調査する
アジアは世界でも最もエネルギー消費量が急増し、かつ原発の開発が最も盛んな地域である。エネルギー開発は経済発展の基盤であるため、各国政府当局及びその関連機関が主体となって行われることが多い。エネルギー政策に関する情報は、従来当該機関に直接ヒアリング調査を行わなければ得ることができなかったが、インターネットが普及するにつれ、比較的容易に入手可能になってきている。
エネルギー政策関連情報は、各国語はもちろん英語でも得ることができる。当然ながら、各国語で得られる情報のほうが多いが、アジア各国のすべての言語に通じることは事実上不可能であるので、アジアの環境情報を比較したり、簡単な調査を行う等の目的のためには事実上の国際語である英語で書かれた情報を調べることになる。
インターネットで情報を得るためには、まずはウェブサイトのURLを知らなければならない。通常、未知のウェブサイトのURLを知るには、Yahoo!等の検索サイトを利用する。しかしながら、当該国の言語に通じていない場合、情報を得たいと思う国の英語情報に行き着くには大きな困難が伴う。Yahoo! 等の一般的な登録制のインターネット検索サイトでは、ある国のURL情報を得ようとしても、英語で得られる情報が極端に少ないのである。例えば、Yahoo! Koreaをつかって韓国の関連機関のURLを知ろうとしても、英語でヒットするエネルギー関連サイトはほとんど存在しない。
しかしこのことはエネルギー関連サイトが存在していないということを意味するものではない。筆者の調査によれば、韓国についてみた場合だけでも下表に示すようなものが存在し、そこで得られる情報の多くが我々日本人にとっても有用である。
「当該国の言語に通じていないため英語情報を得たいが、肝心の英語情報に行き着くことができない」とういう状況は、他のアジア諸国においても同様である。つまり、アジアにおいて各国の英文情報は各国語の情報の中に埋もれてしまっているのである。
また仮にWebページが英語で記述されているインドのような国であっても、Yahoo!等の主な検索サイトには多くの場合登録されていない。Webページをつかって情報を公開している組織であっても、Yahoo!等の自己申告に基づく登録制の検索サイトに自主的に登録を行っている事情があるのだろうが、この場合も当該URLを知るには、大きな回り道をしなければならない。
したがって、こうした回り道や困難を回避するための共有資産をつくるために日本においてアジアのエネルギー・環境問題に関するURL情報を整理することは極めて重要な作業である。ここでは韓国およびインドのWebページの一部を紹介するにとどめたが、詳細なURL情報についてはEINAPホームページで順次公開していく予定である。
【韓国のエネルギー・環境問題関連サイト】
●環境部(The Ministry of Environment)
日本の環境庁にあたる組織。英語ページ有り。環境政策文書、環境ニュース、コンタクトリスト等がある。
●産業資源部(The Ministry of Commerce, Industry and Energy)
日本の通産省にあたる組織。英語ページ有り。各種統計、プレスリリース、各種レポート等がある。
●科学部(The Ministry of Science and Technology)
日本の科学技術庁にあたる組織。英語ページ有り。
●韓国電力研究所(Korean Research Institute of Power)
●韓国原子力研究所(Korea Atomic Energy Research Institute)
●韓国電力(Korean Electric Power)
韓国電力の経営関連統計数値、電源開発目標、電力需給見通し、韓国内の電力に関する統計(発電設備容量や発電量)。
●古里原発
韓国語情報のみ。
●韓国原子燃料会社
http://www.knfc.co.kr/home/mainindex.htm
【インドの環境・エネルギー問題関連のサイト】
●India Image
インドの政府関連サイトの案内サイト。検索ができる。
●MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
環境白書(サマリー)、汚染関連データ(大気、河川)、自然保護関連データ、環境法制、アニュアルレポート、Enviro
News、等。
●The Indian Economy Overview
http://www.nedo.go.jp/report/807/807.html
インドの国家予算、経済の概況。
●Ministry of Power
エネルギー計画、関連資料等。
●http://www.nic.in/powermin/nrg4.htm
エネルギー関連法、政策
●Department of Statistics
統計(一般)
●Ministry of Water Resources
水資源関連プロジェクトや水資源管理計画など。
●India Search com
http://www.indiasearchengine.com/
インドにあるページについての検索サイト。
●USAID India
http://www.info.usaid.gov/india/
環境関連の援助についてのページがある。
●Nuclear Power Corporation of India Limited
インド政府の政策方針に従って原発を運転・建設している国策会社。
●インド、パキスタンの核実験に関する特集サイト(CNN)
http://www.cnn.com/WORLD/9708/India97/index.html
●TERI(Tata Energy Research Institute)
インドの環境問題、エネルギー問題に関する有名な研究所のサイト。情報量豊富。
●INDIA CODE INFORMATION SYSTEM
http://caselaw.delhi.nic.in/incodis/
インドの法律の検索サイト
●Ministry of Non-Conventional Enegy Sources
再生可能エネルギーの開発・普及に関する政府機関
●Indian Renewable Energy Development Agency Ltd
http://solstice.crest.org/staff/mpt/INDIA/ireda.html
2)インターネットを利用した廃棄物関連情報の収集
廃棄物に関する情報収集にあたっては、廃棄物の種類(都市ごみか有害廃棄物か)を特定し、それぞれの廃棄物を所轄する官庁、NGO、国際機関からデータや情報を検索するとよい。
都市ごみは、多くのアジア諸国において地方政府によって処理・処分されているが、ごみの排出量や、データはほとんど把握されておらず、またホームページの設置もほとんどない。したがって、関係省庁にあたらなければならない。関係省庁には、衛生省(Ministry
of (public)Health)、処理上のガイドラインなどは環境省(庁)、また地方政府を所轄する省(庁)がある。
国際機関や対外援助機関の多くは、都市開発(Urban
Development)プロジェクトとして、アジア諸国のごみ処理に関わっているため、各機関の都市開発部門をあたるとよい。国際機関は、インターネット上でレポート類を公開している。
アジア諸国のごみ処理比較を試みたものとしては、世界銀行からレポート("What
A Waste: Solid Waste Management in Asia.")がだされており、ダウンロードできる。
有害廃棄物の越境移動については、バーゼル条約の事務局のサイトが基本的な情報を提供している。締約国会議の資料や、各国が事務局に報告した有害廃棄物の越境移動についての資料を閲覧することができる。
有害廃棄物の越境移動については、バーゼル・アクション・ネットワークのサイトが充実している。新聞情報のクリッピングなど、現在起こっている問題を理解するための情報が整っている。また、1998年末の台湾からカンボジアへの水銀入りの有害廃棄物が輸出された事件では、独自に現地調査を行うなど、有害廃棄物の越境移動の問題についてNGOとして監視を継続的に行っている。
NGOとしては、グリーンピースも有害物質に関するキャンペーンを継続して行ってきている。1999年から2000年には、船でインド、タイ、フィリピン、香港、日本などをまわるToxic
Free Asia Tourを行っている。また、グリーンピースのオーストラリア支部がアジアの有害廃棄物の越境移動について、レポートを発表している。インドやフィリピンでの鉛のリサイクル工場の調査報告などは、工場周辺の土壌中の鉛濃度なども調査しており、グリーンピースの情報収集力や分析力をしめしている。また、グリーンピースは、ダイオキシンなどの発生を抑制するため、ごみの焼却の禁止を訴えている。
【廃棄物関連のサイト】
●Basel
Action Network
有害廃棄物の越境移動に関するニュースをまとめたページなど、情報が多い。
●Green
Peace International
有害物質に関するキャンペーンの中で、有害廃棄物や廃棄物の焼却などを扱っている。
●Green
Peace Australia
http://www.greenpeace.org.au/info/archives/toxic/trade/index.html
フィリピンやインドの廃バッテリーに関するレポートが見られる。
●World
Bankレポート
http://www.worldbank.org/html/fpd/urban/solid_wm/swm_body.htm
●バーゼル条約事務局
締約国会議の資料、条約加盟国のリストなどバーゼル条約についての基本的な情報が入手できる。
●香港環境保護署
http://www.info.gov.hk/epd/waste/index.htm
香港における都市廃棄物・有害廃棄物に関する情報が得られる。レポートや報告書のダウンロードができる。
●Thailand:
MOSTE, Pollution Control Department
Hazardous
Substances and Waste Management Division
DivisionsからHazardous
Substances and Waste Management Divisionを選択する。おもに、有害廃棄物に関するデータベースやガイドラインに関する情報が得られる。
3)インターネットを利用した東南アジアの森林関連情報の収集
東南アジア地域の熱帯林は、世界で有数の森林減少率となっている。それへの警告や危惧は先進国を中心として様々な形でメディアに乗っているが、当該諸国の概況としては十分な情報を提供するに至っていない。しかし、東南アジア諸国の中には情報提供が進んでいる国もあり、その程度に差違が生じてきている。それはインターネットサイトでも然りである。森林資源を減らすことなく利用していくには、実状を専門家のみならず一般市民も理解し、それへ適切に対応をしていくことが欠かせない。つまり、情報の共有が極めて重要と言える。そこで、ここでは東南アジア地域の幾つかの国を取り上げて、森林に拘わるインターネット事情を紹介する。
まず、東南アジア地域の主要な国の関連サイトへは、下記のWorld Resource Institute HP(Homepage)を利用して辿るのが便利である。このサイトに掲載されているのは、Asia、Burma、Indonesia、Japan、Malaysiaである。それぞれの中身を見ていこう。
●World Resource Institute
http://www.wri.org/wri/ffi/internet/asia.htm
(Asia, Burma, Indonesia, Japan, Malaysia)
Asia(Asean)はリンクが張られているものの、リンク先のサイトに入ってみると開設されていない。また、BurmaではNGOと思われるThe Free Burma Coalitionの英語のサイトへ繋がるが、その中に森林関連を主に取り上げた情報は見当たらない。また、このサイトから他のサイトへ張られているリンクは、同国の森林情報を得るのにほとんど有効となっていない。日本の中では、農林水産省森林総合研究所や東京大学農学部附属演習林へのリンクが有益である。特に前者では、関連サイトへのリンクも充実しており、森林関連情報のみならず、学術成果の検索も出来るようになっている。
【日本の森林関連のサイト】
●Forest and Forest Products Research Institute
●Tokyo University Forests
http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/homepage.html
Indonesiaのサイトも開かれていないものが多い。唯一有効なサイトと見なされるのは、下記の通りであり、林業法の概要や地区ごとの関連統計、地図が、主にインドネシア語で掲載されている。
【インドネシアの森林関連のサイト】
●Indonesian Forestry
http://www2.bonet.co.id/dephut/dephut.htm
林業法・統計・地図など
Malaysiaでは、Malaysia Timber Councilのサイトが英語で書かれて充実しており、国や州の行政、FAOなどの国際機関、自然保護団体などのNGO、森林関連企業など様々なサイトへとリンクされている。このサイトにはMalaysiaの森林・林業統計が時系列で掲載されており、その推移や実状を知るのに大いに役立つ内容となっている。地域的な特徴を背景に、統計データが半島マレーシア、サバ州、サラワク州に分けられて掲載されている点は特筆して良い。データのUpdateも良く、半年ほど前のデータを入手することもできる。森林や林業、木材貿易などの関連情報を入手するには極めて重要と言える。また、Malaysiaでは森林や木材の認証に力を入れていることから、それに関連する情報が盛りだくさんである。森林・木材認証は、持続的経営のもとにある森林とそこから産出された木材を対象としてNGOが中心となってラベリングし、ラベリングされた木材のみを貿易しようと言う動きである。近年は、欧米を中心に認証を受ける森林・木材が増えてきており、森林の持続性の観点から更に注目の度合が強まっている。森林・木材認証はFSCのサイトに詳しく書かれており、また環境に配慮した経営を対象とするISOのサイトも興味深い。これらのサイトは情報公開が進んでおり、関係者にはその内容は必見の価値がある。
【マレーシアの森林関連サイト】
●Malaysia Timber Council
●Forestry and Environment
http://www.mtc.com.my/forestry/forestry.html
【森林・木材認証関連のサイト】
●FSC
●ISO
また、Trees for the Futureのサイトでは、Philippines、Indonesia、Thailand、Vietnamで行われている活動に関して300単語程度で簡略にレポートされている。記載内容は詳細とは言い難いが、NGOの活動の一端を垣間見ることが出来る。また、このサイトからのリンクは世界中に張られており、世界の状況を知るのには有益である。だが、東南アジア地域のリンクは十分とは言えない状況であり、同地域の詳細な状況を知るのはなかなか容易ではない。
【北米の森林関連のサイト】
●Logging and Sawmilling Journal
●http://www.saverainforest.net/index.html
●Trees for the Future: Situation Report: SOUTHEAST ASIA
http://www.treesftf.org/asia.htm
このように、東南アジア諸国の開設するインターネット情報をみると、掲載される内容に国による大きな開きがある。更に、使用される言語に英語が一般化されているとは言いにくい。つまり、インターネットを利用して関連情報を収集するのは容易なことではなく、情報収集には多大の時間と費用がかかることになる。よって、各サイトおよびリンクの充実を図ることが重要であり、今後はインターネットと人的な繋がりを活用して、それに取り組んでいく必要がある。
4.3 各国・地域別環境情報源
韓国では、環境問題に関して、政府サイド・民間団体サイドともに活発なインターネット利用が行われている。韓国では環境問題が裁判になることは、皆無ではないが少なく、むしろ立法上の問題として争われることが多い。優れた法律を作ることが国会議員や官僚の業績とみなされているため、社会の実情に比して先進的な法律が作られ、そのあとで市民運動が動き出すという形になることも珍しくない。このような状況のため政府サイドでも市民に自分たちの立場をアピールするため日本に比べて積極的に情報を公開している(必ずしも環境保全の立場に立脚するものではない)。以下にその例を挙げる。
【韓国の政府関連のサイト】
●韓国国会
現行法の検索、第1回国会からの議案一覧(検索機能付き)、国会議員一覧(検索機能付き)、国会議事録など。
●法制処
現行法の検索、新法の解説、立法予告(パブリックコメント)・立法計画など。
●環境部
環境部の部署編成(大気・水質・廃棄物・自然保護等)にしたがって各部署の業務内容を紹介する形でページが構成されている。また環境白書など環境部が発行している書籍や雑誌の原文(全文)を手に入れることもできる。
●韓国資源再生公社
リサイクル事業を行う政府出資機関(日本風にいえば特殊法人)。
●農林部
農業に関する政策を担当。
●農業基盤公社(旧農漁村振興公社)
セマングム干拓事業など、干拓・水資源開発等を担当。
●建設交通部
建設行政と運輸行政を担当。
●韓国水資源公社
東江ダムなど水資源開発、および始華地区の総合開発(埋立から都市開発まで)などを担当している。
●海洋水産部
海洋の環境保全などを担当。
【韓国の市民運動団体関連のサイト】
韓国には、数万名の会員数を持つ大衆的な環境運動団体が存在する。
●環境運動連合
中央と各地の地域組織の連合からなる団体。現在力を入れている対象は東江ダム、セマングム干拓、反原子力など。
ホームページでは、現在力を入れて取り組んでいる課題についてのキャンペーンのほか、過去の声明や報道資料なども読むことができ、韓国の環境問題の全体像を把握するのに助けになる。
●緑色連合
自然保護に力を入れている団体。現在力を入れている対象はセマングム干拓、高圧送電線、「白頭大幹」(朝鮮民主主義人民共和国の白頭山から韓国南端へ続く一連の山地)の保全運動など。
●環境と公害研究会
この団体は大衆団体ではなく、専門家中心の団体である。ホームページでは、機関誌の目次などを見ることができる。
【韓国の一般的なサイト】
その他、特に環境だけをメインにして作られているのではないが、環境に関する情報を集めるのにも役に立つサイトがある。
●ヤフーコリア
Yahoo! の韓国版。「環境」は「社会と人文」の中にあり、200強が登録されている。
●シンマニー
ディレクトリ型サイト。「環境」は「社会・生活」の中にあり、約170のサイトが登録されている。
●ネイバー
ディレクトリ型サイト。「環境」は「社会・文化」の中にあり、300弱のサイトが登録されている。
●アルタヴィスタ・コリア
キーワードを入力して検索するタイプのサイト。「環境」をキーワードにして検索すると295728個の文書が検索され、「公害」をキーワードにして検索すると54701個の文書が検索された。
マレーシアでは、連邦政府がマルチメディア・スーパー・コリドー構想を掲げるなど、情報技術の普及と開発に力を入れているため、他のASEAN諸国に対して相対的にインターネット利用が容易である。環境情報入手は、関連省庁を探すことからはじまる。マレーシアでは、科学技術・環境省(MOSTE)に環境庁がある。生物多様性保全計画はMOSTEが、環境基準などのガイドラインは環境庁が所轄している。その他それぞれの所轄官庁を探さなければならないが、マレー語のみの情報公開のところも多い。
マレーシアでは、土地の開発権限が州政府にあるため、連邦政府はアドバイスやガイドラインの作成をつうじて開発に際しての環境保全にかかわっている。また、90年代以降、上水道、下水処理、医療廃棄物処理、有害廃棄物処理、都市廃棄物処理、環境モニタリングの民営化が相次いで行われている。民営化移行の情報に関しては、これらの民間企業にあたらなければならない。
インターネットによる情報収集に関しては、環境庁のサイトで、大気汚染の状況に関するデータが得られる。環境NGOのサイトには、世界的に活動をするWWFや小規模のものまでさまざまであるが、おもに自然保護に関する活動を紹介したものが多い。下に示したTrEESは、クアラルンプールを中心にリサイクル活動を行う環境NGOである。
環境関連の学部や研究所を持つ大学は、リンクや文献検索も充実している。マレーシアでは、下に示したUKMやUPMがある。これらに加えて、個別環境問題を扱ったサイトがある。下に示したスンガイセランゴールダムのサイトは、原住民の住環境と生態系の破壊が危惧されているダム建設に反対する住民によって作られたものである。このようなサイトは、Yahooのような世界的な検索エンジンで探すことは難しい。マレーシアに関する情報は、JARINGなどのマレーシアの検索エンジンを使うとよい。また、The
StarやNew
Straits Timesなどのオンライン新聞での、記事のキーワード検索で情報を手にいれることもできる。
【マレーシアの環境関連サイト】
●マレーシア科学技術・環境省
http://www.mastic.gov.my/kstas/
年次報告が閲覧できる。
●マレーシア環境庁
http://www.jas.sains.my/doe/dwiindex.htm
環境アセスメントに関する情報が充実している、州別の認可事業内容およびその数が閲覧できる。
●WWF
Malaysia
http://www.geocities.com/RainForest/2701/INDEX.HTML
活動内容の紹介をしているが、情報量は少ない。
●ペナン消費者協会(Consumers'
Association of Penang , CAP)
http://www.capside.org.sg/souths/cap/dev.htm
活動内容の紹介・ニュースレターが、項目別の検索で閲覧できる。
●Malaysian
Nature Society
マレーシア自然保護協会のURL、活動内容の紹介が中心。
●Treat
Every Environment Special Sdn. Bhd. (TrEES)
http://www.w3xs.com/trees/htmls/home_ver3.html
クアラルンプールを中心にリサイクル運動などの活動をしている環境NGOのURL、活動内容を詳細に紹介している。住民へ向けた一般的な環境情報の提供や、スランゴール州内国立公園の開発計画に対する環境影響の懸念などの声明も出している。
●Institute
For Environment And Development (LESTARI - UKM)
マレーシア国民大学にある環境開発研究所のホーム-ページ。
●Department
of Environmental Sciences(Universiti
Putra Malaysia,UPM)
マレーシア総合大学にある環境科学学部のホームページ。リンクが充実している。UPMは図書館のサイトにあるリンクを充実しており、WMSというデータベースではUPM図書館にある廃棄物関連の資料の検索ができる。
●UPM図書館サーチエンジン(MINISIS
Search Engine)
http://202.184.24.3/Minisis/Upmdb/Upmdbhtm/upmh.htm
●Sungai
Selangor Dam
http://www.bxserver.com/concern/
スランゴール州におけるダム開発に反対する住民団体のサイト。
●JICAマレーシア事務所
http://www.jica.org.my/jica/jp-index.htm
●<サーチエンジン> JARING
homepage
4.4 個別の事件・問題の情報源
本年3月、ボパール事件を考える会の代表で1985年以来再三現地を訪れて来た谷洋一氏の案内で、事件から15年を経た被災地の現状を視察する機会を得た。以下では、現地で得た情報にインターネットで得られる情報を交えて紹介する。
被害者や支援団体関係者へのインタビューによって明らかとなったのは、被害者の救済が遅々として進まぬ現状であった。ユニオン・カーバイド社(以下UC)からの補償金は、被災者ではなくインド政府に一括して支払われたため、煩雑な被災認定手続きなどに阻まれて補償金を受け取ることができない被災者も少なくないという。
労働機会を失った女性のために政府が提供した作業所もすでにその大半が閉鎖され、現存する作業所では、被害者が正規雇用者よりも低賃金で働かされている。被害者・支援団体が独自に開設した作業所も、製品が思うように売れず、昨年閉鎖されてしまった。
UCの工場跡地には現在も4000トンに及ぶ未処理の化学物質が放置されたままであり、操業当時の有害廃棄物による周辺土壌や地下水の汚染も深刻である(詳細はGREENPEACEの調査報告を参照)。
一方、事故の責任をとるべきUCのアンダーソン最高経営責任者(当時)は、裁判所の召喚を無視して逃亡中で現在も行方不明となっている。アメリカにおける裁判の進捗状況は、被害者・支援団体のホームページで追うことができる。工場跡地の塀には彼の処罰を求めるメッセージが描かれていた。
被害者は健康への多様な影響に苦しんでいるが、行政の医療は被害者にとっては費用負担が重い。そのため、被害者・支援団体がサムバブナ・トラスト民衆診療所を設立、無料で治療を行っている。彼らは独自のホームページを持ち、サムバブナ・トラストのスタッフ紹介や活動報告だけでなく、被害者の証言集や現地の写真を掲載し、事件の実態を世界に向けて発信している。
ボパール事件のような多国籍企業による企業犯罪の場合、先進国側における支援が特に必要とされる。ボパールの場合、既述のGREENPEACEのほかCorporate Watch、Essential Actionなどの欧米のNGOと相互にリンクし、実際の活動だけでなくインターネット上でも協力を進めている。
このホームページのもう一つの特色は、イギリス人のボランティアの青年が作成し、イギリスのプロバイダを利用して公開しているということである。また、別の青年は、イギリスからインドまでボパールへの支援を呼びかけながら自転車で旅をした際、携帯電話を使い道中の様子を自分のホームページで公開していた。
このように、ボパールの活動は、インターネットを利用したNGO活動や被害者の支援について、新たな可能性を示唆しているといえるのではないだろうか。
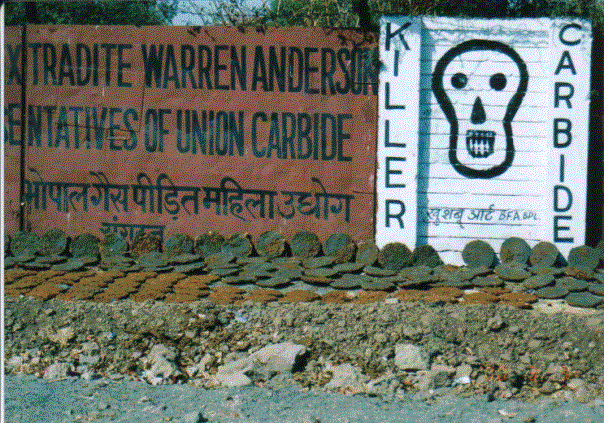
上:UC工場跡地の落書き
 |
|
左:サンバヴナ・トラスト民衆診療所 右:工場付近の少年たち
【ボパール事件関連のサイト】
●ボパール被害者のホームページ
http://www.bhopal.org http://www.bhopal.net/
イギリス人ボランティアのアレックスさんが作成。ディスク・スペースはイギリスのプロバイダのものを利用。被害者の証言集や現地の写真、進行中の訴訟の経過報告、サンバヴナ・トラストの活動報告など、情報も充実。インターネットを利用したNGO活動の好例。
●Life Cycle
http://www.kodex.demon.co.uk/lifecycle/
ボパール被害者支援を呼びかけ、イギリスからインドへ自転車で旅をした青年のサイト。
欧米の支援団体のボパール関連ページ
●Corporate Watch ホームページ
ボパール関連情報
http://www.igc.org/trac/bhopal/listing.html
●Essential
Action(アメリカにおけるボパール・キャンペーンの調整団体)
ボパール関連情報
http://www.essentialaction.org/bhopal/index.html
●Campaign
for Justice in Bhopal
http://www.bhopal-justice.com/
●GREENPEACE or グリーンピースジャパン
http://www.nets.or.jp/GREENPEACE/press/99/release/19991203.html(日本語)
http://www.greenpeace.org/~toxics/toxfreeasia/rembhopal.html(英語)
http://www.greenpeace.org/~toxics/toxfreeasia/bhopal.pdf(工場跡地の汚染調査報告)
5.まとめと展望
以上で見てきたように、本年度はEINAPホームページの充実化を、日本からアジアへの情報発信と、アジアから日本への情報発信の両面から推進してきた。特に、3章・4章に示したアジアの環境情報の収集・公開の活動については、収集された情報の量としても、情報を収集・整理する技術的方法論についても、この一年間に格段の進歩を遂げたといえる。こうした問題別・地域別の情報群の蓄積は、将来的には日本国内だけでなく、アジア地域全体の環境情報の共有に直接的に資するものとなる可能性を持っている。
したがって、今後の活動の発展方向としては、まず日本国内に向けては、「アジアの環境情報」ホームページの充実化を進め、長期的には「アジア環境情報ガイドブック」の出版を目標として活動を進めてゆくべきであろう。先述の通り、本報告書に記載の情報についても、すでにEINAPホームページ上で公開しており、利用者からのフィードバックなどを踏まえて、内容や整理方法について随時改善を進めてゆく計画である。加えて、『環境と公害』に新設コーナーとしてEINAPが執筆を担当する「アジアの環境情報ガイド」を設置し、同誌第30巻1号(7月14日発行予定)から連載を開始する。
また、アジア地域に対しては、蓄積した情報の英文化を速やかに進め、アジア太平洋NGO環境会議などの場を通じて普及を行い、情報の拡充と海外の協力者の募集を継続してゆく必要があろう。
このように、国内においてはアジアの環境情報の拡充を進める一方で、『アジア環境白書』や『環境と公害』などの既存の出版物とEINAPホームページとの連携をはかり、加えて独自出版物の刊行を目指す。アジア地域に向けては、EINAPホームページにおける英文情報の充実化や国際会議などにおける普及活動により知名度の向上を図りつつ、メーリング・リストなどを利用した海外からの協力者の獲得を進める。こうした活動の継続により、将来的にはアジア地域の環境NGOの情報センターとして、ネットワークづくりの一翼を担うことができるよう、経験の蓄積と組織の強化を進めてゆく。